受付時間
定休日:月曜
遺言書セミナー
もめやすい「遺言書」とは?

親の死後に、「財産をどう分けてほしい」「家族がこうあってほしい」などを意思表示するために「遺言書」が書かれることが多くあります。
親が作成した遺言書があれば、残された家族の間ではトラブルを回避できると思っている方もいらっしゃると思います。
ところが、遺言書の書き方や内容により、トラブルが逆に起こりやすくなるケースもあるようです。
そこで、「遺言を書いた方がいいのはどんな人か?」また「遺産の分け方はみんなに任せると書いたらダメ?」、「トラブルにならない遺言書とはどんな遺言書か?」など、さまざまなご質問があります。
そもそも、「遺言書」とはどういうもの
「普通方式」遺言は3種類
遺言書とは、簡単に言うと「親が、死後に自分の財産をどのように処分するかということを書いた書面です。
遺言書は、法律上の要件を満たして初めて有効になり、その効果は国が保障することで、遺言に書かれた相続人に対して法的効力を生じさせる文書ということになります。
遺言書には「普通方式」と「特別方式」があります。
特別方式とは、緊急事態等などの特別な状況におかれた場合に簡単な方法で遺言を認めるものです。
一般的には使われないため、通常使う「普通方式」という方法について解説します。
この普通方式遺言には、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3つが使われます。
(1)自筆証書遺言
自分一人で作成できますので、費用もかからず最も手軽な遺言書です。
しかし注意しないといけません。それは、自筆証書遺言が最も要件は厳しく、無効と扱われるケースも高いものです。
自筆証書遺言が有効とされるには、作成者の➀署名➁押印や③作成日付が本文中に存在していないといけない他に、④遺言書全文が自書されていることが必要になります。
もちろん、日付も自書しなければなりませんし、財産目録は機械(PCなど)を用いて印字してもいいことになりましたが、財産目録の各ページには署名押印を行う必要があります。
この➀〜➃の内で一つでも書いてないと無効となり、遺言として利用することができなくなります。
また、自筆用証書遺言は、保管場所についての法律上に規定はありません。
一人で費用もかからず作成できる点はメリットですが、➀要件違反による無効、➁文賞の意味が不明確で特定することが不能の場合は無効となり、紛失、偽造、改ざん、故意の隠滅などにより、遺言者の意思が達成されないリスクが多分にあります。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、原則として公証役場に行って公証人の面前で遺言者が遺言内容を口授して、公証人はこれを筆記することで作成される遺言書です。
公証役場で事前の打ち合わせをして作成される点で多少の手間がかかりますし、一定の作成手数料が費用としてかかります。
さらに、2人以上の証人の立ち会いが必要です。
デメリットして手間や費用がかかりますが、公証人という法務大臣から任命された専門家が関わりますから、法律上の要件違反により無効や、第三者による偽造のリスクはないことになります。
なお、作成した公正証書の原本は公証役場で保管されますから、紛失や改ざんの危険はありません。
また、相続人等は公証役場による「遺言検索システム」を利用できますから親族等は遺言の存否を照会することができますから、遺言の存在に気付かないというリスクも低減されました。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の存在について、公証人と証人2人に証明させ、遺言内容を公証人も含めてすべての人に秘密にできる遺言作成方式です。
遺言書の存在は公的に証明されますから、遺言書の不存在として扱われる危険性は低いですし、遺言内容を誰にも知られずに作成できる点はメリットです。
11,000円の手数料で公証役場において作成できますから、(2)の公正証書遺言の手数料よりずいぶんと安価になりますす。
ところでが、公証人は遺言の作成に関与しませんから、要件の違反や無効や記載内容不明確・特定不能といったことで無効と解釈されるリスクは、(1)の自筆証書遺言と変わらないことになります。
しかし、遺言書の保管は作成者が自分で行わないといけないため、紛失や第三者によるすり替え、改ざんなどの危険性が残こることになります。
秘密証書遺言が有効と認められるには、
➀遺言者が遺言書に署名・押印すること
➁遺言書の封を閉じ、証書に用いたのと同じ印鑑で封印すること
③公証人1人および証人2人以上に封書を提出し、自身の遺言書であることと、作成者の氏名・住所を述べること
➃公証人がその遺言書を提出した日付と、遺言者の申述内容を封紙に記載した後に遺言者・証人と共に署名押印すること
こうした要件を満たす必要があります。
なお、秘密証書遺言は、遺言書としてのリスクも大きく、その上メリットに乏しく、さらに手続きが煩わしいので、実務ではあまり利用されていないのが現状です。
遺言書を作成した方がよい人、逆に、作成しない方がいい人とは?
遺言書は、まったくの資産が無い方を除き、ほとんどの人で作成した方がよいでしょう。
それは、遺言がなければ利害関係人である相続人が、遺産の分割方法を協議して決めなければならなくなり、そうなると親に近い人と遠方にいる人の情報格差によって相続人の間で不信が生まれたり、意見の対立により相続人は大きなストレスを伴ったりするのが相続の世界だからです。
遺産分割は大きな精神的な負担を遺族に与えます。
場合によっては、相続人間の関係を完全に破綻させるきっかけとなる場合は多いのです。
この事態を避けるためにも、遺産の分割方法は、遺言を通じて親が責任をもって決めておいてあげることが好ましいといえます。
「遺言書がある」ことでトラブルになるケースは?
遺言書は「家族がもめないため」に作られるイメージがあります。
しかし、皮肉にことに「遺言書がある」ことによりトラブルに発展するケースも実際にあります。
それは、典型例ですが遺言の内容が一部の相続人に極端に有利なケースです。
それにより、他の相続人にとっては不利になる場合です。
もっとも分かりやすい例ですと、「全ての遺産を長男に相続させる」とだけ記載された遺言の場合です。
この遺言は、長男以外の法定相続分を完全に無視しており、さらに、このような遺言を作成した理由も記載していない遺言のケースでは、他の相続人が不服を感じ承諾しないでしょう。
この場合に多くの長男以外の相続人は、厚遇された長男に対して遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
さらに、遺言の有効性自体が争われる可能性もあります。
典型的な例では、子の一人が親の名前を偽り偽造し、長男に有利な遺言書を作成したというような場合や、認知症などにより、遺言書の内容を遺言者は理解できていないような状況が主張される可能性もあります。
相続で、残された家族が「もめやすい」か「もめにくい」かは、どんな書き方や内容の遺言書だと起こるかについて触れておきます。
それは、遺言の中に、結論だけではなく、何ゆえにそのような遺言を書いたかという経緯や理由を記載していない場合に起きます。
そこで、相続分に差を設ける場合、特定の遺産について相続人を指定する場合など、「なぜそのような判断をしたか」ということを記載することで、法定相続分をもらえなかった相続人や、欲しがっていた遺産を相続できなかった相続人は、遺言者の思いを理解し、受け入れるためきっかけとなるのです。
さらに、長男以外の子に対して生前にしてあげたことに差があるような場合には、相続で何も手を打たないと、遺産分割の場面では、不足を主張する子は優遇されていた子に、特別受益を主張して遺産で不足分を清算してほしいと激しく争うケースがみられます。
親から見ると、子の一部を優遇することには、それなりの理由があります。
しかし、相続人の間で遺産分割で清算することが望ましくないと考える親は、遺言の中に『持戻し免除』と呼ばれる条項を入れることで、特別受益を理由とする遺産分割の争いの発生を防止することもできます。
遺言書でトラブルならないための作成注意点は
まずは、遺言を作成した理由で相続人に不信を抱かないように注意が必要です。
紛争を予防する観点でいうと、相続開始時に法定相続人の地位に立つことになる人に対して、遺言を作成したことや遺言書を作成しようと考えた理由などを伝えるべきです。
このときに、決して遺言内容自体を相続開始時に法定相続人の地位に立つことになる人に対して(推定相続人という)、また相続人と関係がある人に話さないようにしましょう。
推定相続人としては、遺言の内容を知りたがる気持ちは自然なことですが、ここで伝えると、「親は冷たい」と考える推定相続人は、遺言者に対して意趣返しとして逆に冷たい態度を取ったり、「遺言の撤回」や、自分に有利な遺言を書かせようと画策を行ったりするなど、相続前に新たなトラブルの引き金になりかねないとお考え下さい。
遺言書の作成は、費用の許す限り、「公正証書遺言」が望ましいと考えます。
偽造や改ざんの防止や、遺言の効力を発揮できる可能性も高く、遺言者の意思を相続で明確にできる手段といえるからです。
注意してほしいことがあります。
それは、公証人は遺言内容自体についての相談に応じてくれることはありません。
この点を多くの方が誤解しています。
不動産、株式などを保有している場合には、遺言内容をどうすべきか、相続に詳しい相続相談福岡センターに事前相談をして頂きたいのです。
そのサポートを受けながら遺言内容を確定して遺言書の原案を作成し、公証役場に持参して、公正証書遺言の作成を行い、保管してもらうようにすることがベストな遺言作成の方法であると思います。
遺言書セミナー

遺言書の理論ではなく実践をお話しします
最近は「老後の終活の心構えとは」「遺言は必要?」という皆様の声をよく聞くようになり、終活のための遺言についてもご高齢者の高い関心をお持ちの方が増えていると感じています。
しかし、
「本当に遺言書は必要なのか?」、「遺言書を残すメリット・デメリットは?」、「なぜ相続に必要?」といった疑問や悩みをお持ちのご高齢者が多くいらっしゃると感じています。
私たちのセミナーに参加された方の中にも法的なことや相続手続の問題点などかなり専門的なことについて悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたが、「遺言書とはそういうものだったのか」、「手続きなどが明白になった」と基本的な遺言書についての理解が進んだというセミナー参加者のお声を多くいただきました。
いつ遺言書は残されたご家族へ想いを伝えるお手紙です。
人と人とのつながりを最期まで大切にしたいとお考えの方には特に遺言書の作成をおすすめいたします。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のサービス個別ページ2サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。
サービス個別ページ2に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
※ページを最後まで読んでくださったお客さまへのメッセージと、お問合せへ誘導するための文章を記載してください。
遺言書サービスのご案内
遺言書セミナー

遺言書
作成サービス
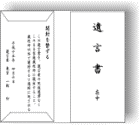
相続手続き
おまかせパック




