受付時間
定休日:月曜
選ばれる理由
遺言書は作成がゴールではない!
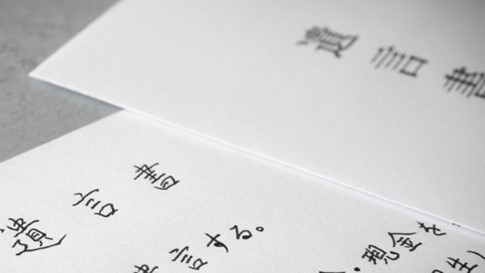
遺言書の作成はゴールではない!
遺言の内容を確実に遺言執行が
できるかどうかの問題
自筆証書遺言の保管制度が2020年に始まった。
利用の累計が8万件に達したそうだが、公正証書遺言の作成件数も増加傾向にある。
ところが、残念ながら自筆証書遺言は不備が多く、役に立たないこともある。
問題は、役に立たないことに気付くのは作成者本人がお亡くなりになった後だからである。
ここで、作成済の遺言書をチェックする場合のポイントを確認しておきましょう。
作成した遺言書のチェックポイント
1. 遺言書の要件を満たしているか
2. 「相続させる」「遺贈する」など、正確な文言が使われているか
3. 遺言内容の変更はないか
4. 不動産情報は登記内容と合っているか
5. 相続人等が不存在になったときの手当として予備的遺言がなされているか
6. 遺言執行者に変更はないか、予備の遺言執行者はいなくて大丈夫か
7. その遺言執行者で問題はないか
残念ながら、遺言相談福岡センターが関与した自筆証書遺言では、これらをすべて満たしている遺言は、まれです。
また、公正証書遺言でも遺言者が直接公証役場に行き作成した遺言書と、専門家が関わる遺言書では異なっているケースが多数あります。
それは、「前者は公証人が内容の詳細を把握して遺言書を作成するわけではないため、時間の経過や状況の変化などで実行が不可能になる」こともあるのです。
まず、確認するのは内容に不備があるかどうかです。
たとえば、「自宅は妻に、預貯金は子どもに相続させる」という内容の公正証書遺言があったとします。
もし、妻が先に亡くなった時に遺言者の認知機能が衰えていたら遺言者が再度作成し直すことは難しくなります。
さらに、予備的遺言で、妻が遺言者より前に亡くなっていた場合には誰に相続させるかという記載がなければ、妻に相続させるはずだった遺産は宙に浮いてしまいます。
宙に浮いた遺産は遺産分割協議の対象になり、家族間でもめる原因になります
その次に確認するのが、遺言執行が可能かどうかです。
高齢化で相続人に認知症のある人がいたり、代襲相続人が含まれるケースも珍しくありません。
相続人もそうですが、遺言書で指定している遺言執行者が認知症になることも考えられますし、利害関係人がいなければ遺言が執行できなくなります。
そのために、専門家が遺言書を作成する場合は状況が変化しても対応できるように、一度の作成で済む内容にするのが基本となります。
さらに高齢になると、夫と妻、どちらが先に亡くなるか分からないため、どちらになっても執行ができるようにしておくことが重要になります。
みなさんは、遺言書を書くことを目的にしますが、専門家からみれば執行のできない遺言書では意味がないのです。
専門家が関与していれば不動産の登記簿謄本を取得して、所有者を事前に確認します。
一方で、自筆で作成する場合に所有者を確認をすることは少ないため、「長年にわたって住んでいるから自分の名義だと思っていたら、父や祖父の物だった」ということも起こりえます。
自筆証書遺言を法務局が保管する制度を利用したとしても、この保管制度は
➀有効な遺言書が保管される、
➁紛失や偽造の恐れがない、
③遺言者が亡くなると相続人に遺言書の保管通知が届く、
④検認が不要という利点はあるけれど、そもそも内容に不備がある遺言書の場合も あるのです。
法務局は、有効な自筆証書遺言を保管するだけで、内容の不備を指摘はしないし、できないのです。
しかし、自筆証書遺言にせざるを得ないこともあります。
それは、余命宣告された、体調が悪化したなどの遺言書の作成を急ぐケースでは、公正証書遺言では間に合わない可能性もあり、ある程度の簡単な文面でも遺言書を作成しておいた方が良い場合もあります。
相続相談福岡センターの関与する公正証書遺言作成の流れ
1. 相談
所有不動産、所有財産、遺言したい内容などを聞きながら、遺言内容に関する注
意点や対策方法などをアドバイス
2. 相続内容の方向性を決めて必要書類の収集
➀遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の続き柄が分かる戸籍謄本、財産を法定 相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
➁相続財産を確認できる資料
不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書、
預貯金、株式などの有価証券、借金など財産の種類や額が確認できるもの
③遺言者が証人を用意する場合
証人の住所・職業・氏名・生年月日がわかるもの
3. 遺言書原案作成
A.遺言者が直接公証役場で作成する場合
遺言者が公証役場の予約をして、
必要書類を持参する。公証人に遺言内容を伝える。
B.行政書士などの専門家につなぐ場合
遺言者に引き合わせ、必要情報を伝える(戸籍謄本などの取得を専門家に依頼す
る場合は、遺言者は印鑑登録証明書のみを取得。その後の細かい手続きなどは専
門家が行ってくれる)
4. 公証人と調整、公正証書遺言作成日時を決定する
・公証人から届く遺言書の下書きの内容を確認。修正や変更などがなければ、
公証人、遺言者、証人2人の予定を確認して予約する。
(Bの場合は専門家が行う)
5. 公正証書遺言の作成当日
➀公証人が遺言者、証人、本人の確認を行う
➁(Aの場合)公証人が遺言内容を読み上げる
(Bの場合)公証人が遺言者に遺言内容を聞き、下書きと内容の一致を確認後
遺言内容を読み上げる
③遺言者、証人が遺言内容を確認、原本に署名押印する
➃公証人手数料を支払い、遺言書の正本、謄本の交付を受け取る
高齢者の相続で起こりがちなトラブルを防ぐ
高齢者夫婦のケースでは、間を置かずに亡くなるケースも珍しくないので、2次相続も想定しておくことが多くなってきています。
妻も遺言書があったほうがいい場合は、一緒に作成しています。判断能力の低下は徐々に進むことが多いものですが、病気や入院で一気に進むケースもあり、時間との戦いになること増えています。
夫が遺言書を作成して、先に妻が亡くなると妻の財産の多くが夫にいきます。
その後、夫が亡くなったら妻の財産も両方合わせた財産が遺言の内容になります。
妻が先に亡くなることも想定して遺言執行ができるように作ります。
さらに相続税がかかるのか、小規模宅地等の特例が使えるのか、二次相続の時に相続税がかかるのかなど税金面を考慮することも大事です。
しかしながら、公正証書遺言で作成する場合は、さまざまな対策をした方がいいとわかっていても、遺言者の希望を優先した方がいいこともあります。
とくに、遺言者が高齢の場合、心掛けていることはシンプルな内容にすることです。
教科書通りの対策からは少し外れ、たとえ税金を少し多く払うことになっても、無事に公証人の前で遺言内容を言えなければ、作成ができないからです。
ただし、明らかに特定の相続人に偏りすぎた内容だと、後から揉める原因になることもあるので、配慮する必要があります。
遺言者の思いや遺言作成の理由を付言事項に入れておくことも大切です。
最後に、遺言書を作るなら早めがいいと考えます。
おおむね80歳を越えると作成も対策のやり直しも難しくなるからです。
遺言相続福岡センターでは、高齢者の方から遺言作成のご相談をお受けする場合には、とくに遺言者にとってラストチャンスと思って取り組みをさせて頂いております。
どうぞ、相続相談福岡センターにお気軽にご相談と、そしてお問い合わせください。
当事務所のセミナーが選ばれる理由についてご紹介します。
分かりやすいセミナーで老後問題を解決

セミナーで、高齢女性の老後問題を解決するお話をします。相続問題を解決し、安心の老後生活を実現できます。
その方法はセミナーの中で!
任意後見契約書や遺言書の書き方などもサポート
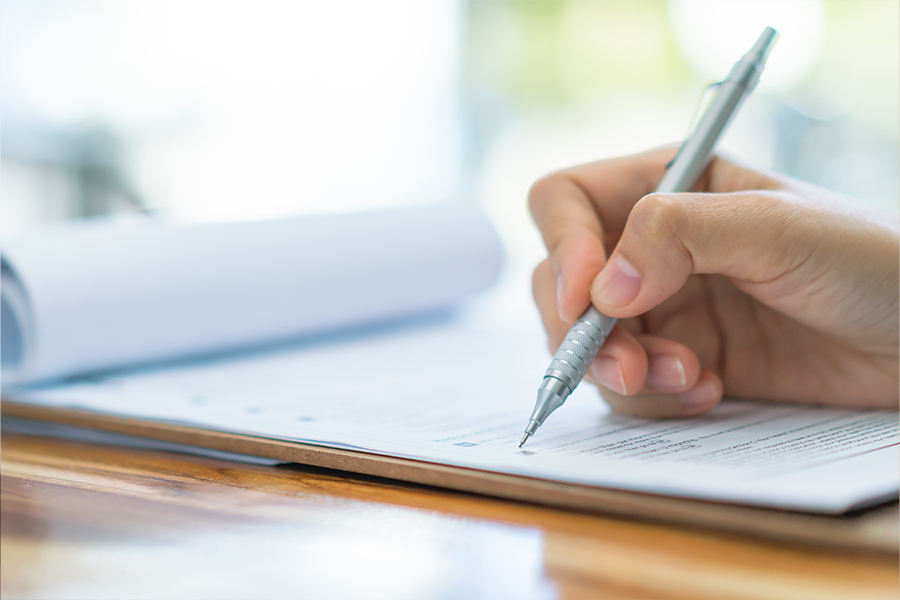
セミナーの他、お客さまが相続争いにならないような遺言書の作成のサポートも行います。
任意後見契約書では、元気な今から終活の最後の時にも対応できる内容で作成します。
経験豊富な行政書士が相続トラブルにならないための終活のアドバイス

1,000件以上の遺言書作成実績、300件以上の任意後見契約書の作成実績がある行政書士が登壇します。セミナーでは失敗した相続の実例もお話しています。
遺言書の作成では多くの方が費用優先で作成されます。そして、自筆証書遺言を作られています。当事務所では痒いところに手が届く遺言を作成します。それが、安心の遺言です。
任意後見契約は家裁でも相談は聞いてくれません。なぜなら実務体験が無いのですから。相続に関するプロが、安心の任意後見契約書を作ります。



