受付時間
定休日:月曜
遺言書が必要な人

遺言書が必要な人
最近の家庭裁判所で行う遺産分割の調停件数は増加傾向にあり、公正証書遺言や法務局で預かる自筆証書遺言の作成件数もかなり増えています。
「うちには遺言書なんて必要ない」とお父さんが決めつけると、残された家族が大変な思いをすることになる可能性があります。そこで、「遺言書が必要な人」について考えてみましょう。
遺言書が必要な人とは
民法では、相続人や遺産を相続する割合は、以下の通りになります。また、遺産の配分順位や割合は、民法900条で定められています。
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
④ 直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
相続人が「配偶者と配偶者との子供が1人」「成人した子供が1人」という場合に遺言書を作成する必要性は必ずしもありません。
ただし、前記の場合以外は、遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
遺言書はなぜ必要?
まず最初に、遺言書を書くべき理由は、家族や親族内における遺産分割協議で起こるもめごとを避けるためです。
遺言書がない場合の相続手続では、法定相続人全員が集まって「遺産分割協議」をします。ところが、法律で配分順位や割合が決められていても、争続になるケースは年々増えているのはなぜでしょうか。
「うちは遺言書なんて必要ない」と思っている方はお父さんが多いですが、時代がそうさせるのか、家族や親族の遺産分割調停の事件数が増加しているのです。
最高裁判所が発表している、家事事件「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別」の全国総数でも増加傾向ははっきり出ています。
家事事件「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別 」
平成21年は10,741件だった遺産分割事件数は、平成30年には13,040件で121.4%に増えています。
このグラフは「実際に遺産分割調停を起こした」ケースですから、裁判を起こすまではいかなくても、遺産分割協議でもめている家族等は更に多いことは示しています。
このような争続を避けるためか、遺言公正書を作成している件数も年々増加しています。
日本公証人連合会「平成30年の遺言公正証書作成件数について 」
平成21年は77,878件だった遺言公正証書作成件数が、平成30年には110,471件の141.8%増になっています。
この10年間で約3.2万件の増となっていますが、背景には「遺産分割協議で家族内のもめ事を避ける」という親の思いが現れています。
遺言書はいつ書くべきか?
「遺言書は死期が迫って作る」というイメージが多くの方が持っているとおもいますが、実は遺言書を必要とする人は今すぐ作成してください。
事故などが突然起こることも考えられますし、一番残念なことは加齢とともに人間の判断能力は衰えていくということです。
遺言書は15歳以上の方であれば作成ができますし、作成年度によって遺言書が無効になることはないからです。
遺言書が必要な人には、元気な「今」が遺言書を作成する最良のチャンスです。
※ターゲットの悩み(orニーズ)を記載し、その悩みに共感する文章をご記入ください。
例)肩こりが辛くて仕事に集中できないと悩んでいませんか?
私も以前は肩こりに悩まされる日々が続いていました。
※また、上記を記載した後に、このページを読んだら何がわかるかを簡単にご記載ください。
※お悩みがイメージできるような写真や素材画像を挿入していただくと、より効果的です。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
遺言書が必要な人について
遺言書が必要な人について
遺言書が必要な人①…相続人の間で遺産の取得分を決めておきたい人
その①の理由は、「遺産の所得分を遺言で決めておきたい人」です。そこで、「遺産の取得分を決めておいたほうがよい人」の例を紹介しておきます。
【配分を決めたおいたほうが良い人の例】
(ア) 遺産で不動産の割合が多い方
(イ) 相続人の人数が2人以上いる
(ウ) 結婚しているが子がいないご夫婦
(エ) 事業を経営している方
(オ) 相続人の兄弟仲が悪い
(カ) 家族の中に援助が必要な方がいる
援助が必要な相続人(障がい者や未成年の子供)がいるケースでは、相続人以外の後見人を遺言書で選定するなどしておけば安心です。
少し解説しておきます。
●不動産の割合が多い方(含む、遺産は自宅のみの方)
不動産の割合が多い方や、もしくは自宅しか財産がないケースでは、遺産分割協議が難しくなることが考えられます。不動産が複数ある場合でも、同じ評価額の不動産を均等に分割できればよいですが、不動産には同じものが一つもないからです。
また自宅しか不動産がない場合、相続人が2人以上いれば不動産を現物分割・換価分割・代償分割という3つの方法を使って分けるという選択しなければなりません。
もしも、不動産に相続人の内で誰か住んでいる場合、遺産分割の結果、その相続人が自宅を売却などで失うことになります。遺産相続では不動産が特にもめやすいこともあるため、遺産の中で不動産が多い(自宅しか財産がない人)は、遺言書で争わない対策を必要な人と言えます。
●相続人の人数が2人以上いる方
相続人が2人以上は、「配偶者と子供1人」「子供が2人以上」というケースだけではありません。
先妻と後妻のそれぞれに子がある場合、先妻とは婚姻関係にないために相続する権利はありませんが、先妻との子は権利があります。先妻の子と後妻の子の関係によっては、遺産分割方法や相続する遺産の内容でもめることが考えられます。実子と養子がいる場合や嫡出子と非嫡出子がいる場合も、同じです。
この他では、すでに両親が他界していて未婚で子がない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。あなたの兄弟姉妹がすでに他界している場合は子(甥・姪)が代襲相続人になりますが、このケースでは相続人の数が多くなります。もし、遺言書がないと、遺産分割協議でもめることは必ずといっていいでしょう。
●結婚しているが子はない
配偶者は常に法定相続人ですが、子がない場合はあなたの父母や兄弟姉妹にも相続の権利が発生します。また、前妻との間に子がいる場合、前妻には権利がありませんが子には権利はあります。
この場合にあなたが配偶者へ100%遺産の相続をさせたくても、遺言書がない限りは父母・兄弟姉妹・前妻の子にも相続する権利があります。
もしも配偶者と他の相続人の関係が悪い場合、遺産分割協議ではめることが予想されます。
●事業を経営している方
法人化しているか法人化していないに関係なく、事業を経営している方も遺言書が必要な人と言えます。法人化して事業を経営している場合は、会社の株式を誰が相続するかで事業継承に大きな影響を与えます。
また個人事業を経営している方の場合、事業資産はほとんど個人名義のためこれらは相続財産の対象となります。この場合には遺言書を作成する他に、生前に事業継承をする方法もあります。
〇〇〇〇〇〇(解決方法)

2.法定相続人以外に
遺産を遺したい人も遺言書が必要
「法定相続人以外の人に遺産を遺したい(遺贈といいます)人です。
法定相続人以外の人(遺贈したい人)は次のような方々です。
・内縁関係の妻(夫)
・養子縁組していない配偶者の子
・配偶者の親族
・代襲相続人でない孫・祖父母・甥姪
・婿や嫁や従妹
・血縁関係のない友人等
法定相続人とは、あなたの配偶者・子(嫡出子ではない子・養子含む)・父母・兄弟姉妹といった家族になります。
法定相続人が他界している場合の子の孫や父母であれば祖父母・兄弟姉妹等の直系が代襲相続人となります。
法定相続人以外の方に遺贈したい場合には、遺言書がないと遺産を分けることはできません。お世話してくれる人に遺産を遺したい方は、遺言書の作成が必須です。
2.相続させたくない人がいる人
相続をさせたくない法定相続人がいる方
相続をさせたくない相続人がいる方は、遺言書が必要と考えられます。たとえば、親不孝の子や、会ったことがない前妻の子、虐待を繰り返した親などです。
しかし、相続をさせたくない方が第一順位の子や第二順位の親である場合には、「遺留分」という権利があります。この場合には遺言書に記載するのではなく、「遺言による廃除」を行う必要があります。
相続をさせたくないのが兄弟姉妹であれば、これらを行う必要はありません。
マイナスの遺産がある
相続では現金や不動産などの財産だけではなく、借金によるマイナスの財産も相続の対象となります。
法定相続人が親の借金などマイナスの財産があることを知らない場合、遺言書に書きのこしておかないとマイナスの借金まで相続してしまう可能性があります。マイナスの借金などがある場合は、遺言に書き遺して記載しておきましょう。
というのも、借金などのマイナスの財産は相続後3ヵ月以内に手続きをすれば、「限定承認」や「相続放棄」という手続きが残されるためです。
遺言書や財産目録に書き残しておけば、法定相続人に遺産を相続するか放棄するかの時間的な猶予を与えることができます。
法定相続人がいない方
「法定相続人がいない方」には遺言書が必要です。法定相続人が「いない方」には、「法定相続人が行方不明」という場合と「家族や親戚がいない」という2種類のパターンがあります。ここでは2つの「いない」パターンのお話をします。
法定相続人が行方不明で分からない
法定相相続人が行方不明で住所等がわからない、そもそも会ったことがない法定相続人がいる場合には、遺言書が必要です。遺言書がないと相続の問題以前に、相続人の間で遺産分割協議ができないからです。遺産分割協議は法定相続人全員が揃いしかも全員の合意がないと遺産分割はできないからです。
法定相続人のうち1人が行方不明の場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てるか、相続手続をするのに不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。遺言書を作成しておけば遺産分割協議が必要ないため、遺言を書いておくことが必要になります。
家族も親戚もいない
法定相続人がいない場合には、その方の遺産は民法959条によって「国庫に帰属される」ことになります。なお、生計を共にしている内縁者や家族同然の友人知人がいる場合に遺言書を作成しておけば遺贈できることになります。
遺言書がない場合に法定相続人以外の人が「特別縁故者」の申し出をして、家庭裁判所に認められると財産分与が受けられます。
※この要素には、以下の2つをご記入ください。
・具体的な解決方法の解説
・その解決方法で解決できる根拠(理由)
※解決方法がイメージできる写真や素材画像を入れていただくと、より効果的です。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ンあいうえおか
きくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
それでも〇〇にお困りなら
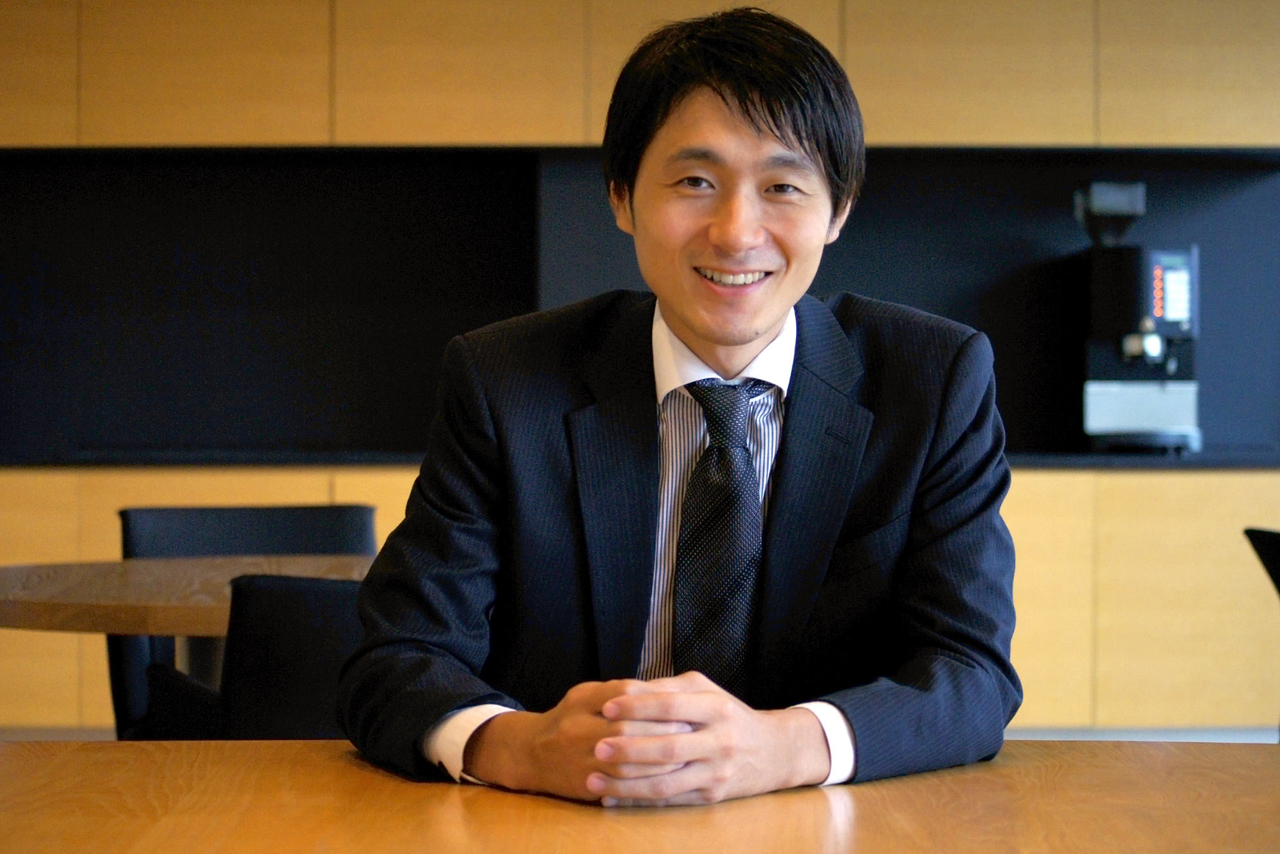
例)○○○代表の○○です。
あなたのお悩みを解決します!
※お役立ち情報ページに直接アクセスしてきた方へ、御社のサービスをご紹介してください。
この要素には、下記3点をご記入ください。
・ページ最上部で記載したお悩みやニーズを、御社のサービスでも解決できること
・そのお悩みを御社のサービスで解決できる根拠(理由)
・サービスの概要
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやエオカキクケコサシスセあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもや
※3点を読ませた後に、該当するサービスページへのリンクを張ってください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。




